
猫という名前はいつの時以来使われるようになったのでしょうか?
猫にはさまざまな名前の由来があると言われていますが、ここでは有力な説や、一般には知られていない説まで掘り下げてみます。
また、猫の漢字の成り立ちについても探ります。
※本コラムでは便宜上、「ねこさん」を「猫」と表記しています。
日本語の「ねこ」の語源
「寝子」からきた説
最も有力な説は、猫が長時間寝る性質から「寝る子」と呼ばれ、それが短縮して「ねこ」になったというものです。
猫は一日の中で14時間以上寝ることが常で、子猫の場合は20時間以上寝ていることもあります。この説は広く受け入れられています。
実際に猫は「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」といわれる習性を持ち、明け方や夕暮れ時に最も活発になります。
そのため、昼間は長時間寝てエネルギーを蓄えるのが普通です。こうした生態が、「寝る子=ねこ」の語源として根付いたのでしょう。
「ねうねう」という鳴き声説
昔の人々は猫の鳴き声を「ねうねう」と表現していました。
そこに「子」をつけて「ねうねうこ」と呼ばれるようになり、やがて短縮されて「ねこ」になったという説です。
日本語では昔から、親しみを込めて小さなものに「子」をつける習慣がありました。
たとえば「犬子(いぬこ)」や「雀子(すずめこ)」なども使われていたといわれています。その流れから「ねこ」という名前が定着したのかもしれません。
「ねこま」説
平安時代の書物には「ねこま」という表記も見られます。
これは「寝るのが好きな魔物」という意味を持つとされ、「寝小魔(ねこま)」という当て字も使われていました。
また、猫がネズミを捕まえることから「鼠の神(ねこま)」とされ、ネズミを退治する守り神のような存在だったとも考えられています。
「鼠小待(ねこま)」や「鼠好(ねこま)」といった当て字もあり、猫とネズミの関係性が深かったことがうかがえます。
猫の漢字の成り立ち
猫を表す漢字「猫」は、「けものへん」に「苗」が使われています。この理由には二つの説があります。
鳴き声に由来
中国では猫の鳴き声が「ミャオ」や「ミョウ」と表現されることがあり、「苗」の発音と関連していると考えられています。
これは、中国から猫が伝わった際に、漢字の成り立ちにも影響を与えたのではないかとする説です。
猫の動きを表した説
「苗」は、土から芽を出して成長する細くしなやかな姿を表します。
猫もまた、柔軟でしなやかな動きをするため、その特徴を漢字で表現したのではないかとされています。
猫は高いところから落ちても体勢を立て直して着地できるほど、しなやかな体を持っています。
そのしなやかさを「苗」に例えた結果、現在の「猫」という漢字ができたのかもしれません。
海外における猫の名前の由来
日本語の「ねこ」だけでなく、海外でも猫にはさまざまな名前が付けられています。
- 英語(cat):古英語の「catt」から派生し、さらにラテン語の「cattus」、ギリシャ語の「katta」に由来するとされています。古代エジプト語では「caute」とも呼ばれていました。
- フランス語(chat):ラテン語の「cattus」が語源で、「シャ」と発音されます。
- ドイツ語(Katze):同じくラテン語の「cattus」に由来し、ドイツでは古くから使われている名前です。
- 中国語(猫):発音は「māo(マオ)」で、鳴き声の「ミャオ」に由来していると考えられています。
日本の古典に登場する猫
日本の歴史書や文学にも、猫に関する記述が見られます。
- 『今昔物語集』
平安時代の説話集で、猫が貴族の家で大切に飼われていたことが記されています。 - 『徒然草』
鎌倉時代の随筆で、猫の賢さや愛らしさが語られています。 - 『源氏物語』
平安貴族が猫を愛玩していた様子が描かれています。
猫に関する神話や伝説
猫は世界中の神話や伝説にも登場します。
- 古代エジプト
猫は神聖な動物とされ、バステト神(猫の姿をした女神)が崇拝されていました。 - 中国
猫は幸運をもたらすとされ、特に金運や商売繁盛に関連付けられています。 - 日本の妖怪伝承
化け猫や猫又(ねこまた)など、猫が妖怪として描かれることもありました。
猫にまつわる日本の文化
猫は日本の文化にも深く根付いています。
例えば、江戸時代には「招き猫」が商売繁盛の縁起物として広まりました。寺社には猫を祀ったものもあり、人々の生活に欠かせない存在だったことがうかがえます。
また、猫に関することわざも数多く存在します。
「猫に小判(価値がわからない)」や「猫の手も借りたい(忙しい)」など、猫の特徴をとらえた表現が使われてきました。
まとめ
猫の名前の由来にはさまざまな説があります。「寝る子」から「ねこ」になったという説が最も有力ですが、鳴き声由来説や「ねこま」という古い表記からの派生説など、興味深いものがいくつも存在します。
また、「猫」という漢字の成り立ちを知ることで、猫に対する昔の人々の認識や親しみが見えてきます。海外の猫の名前の由来や、日本の歴史・伝説に登場する猫を知ることで、さらに猫の魅力を感じられますね。


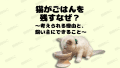
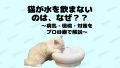
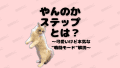

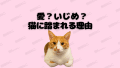
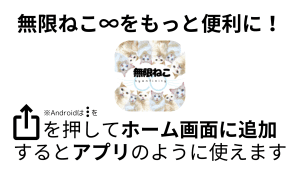
コメント