「うちの猫、あまり水を飲んでいない気がする…」
そんな不安を感じたことはありませんか?
実は、猫は“あまり水を飲まない動物”として知られています。
とはいえ、あまりにも水分摂取が少ないと、健康に影響が出る可能性も。
この記事では、猫が水を飲まない理由とその背景、
放っておくことで起こりうるリスク、
そして自宅でできる水分補給の工夫をまとめてご紹介します。
※本コラムでは便宜上、「ねこさん」を「猫」と表記しています。
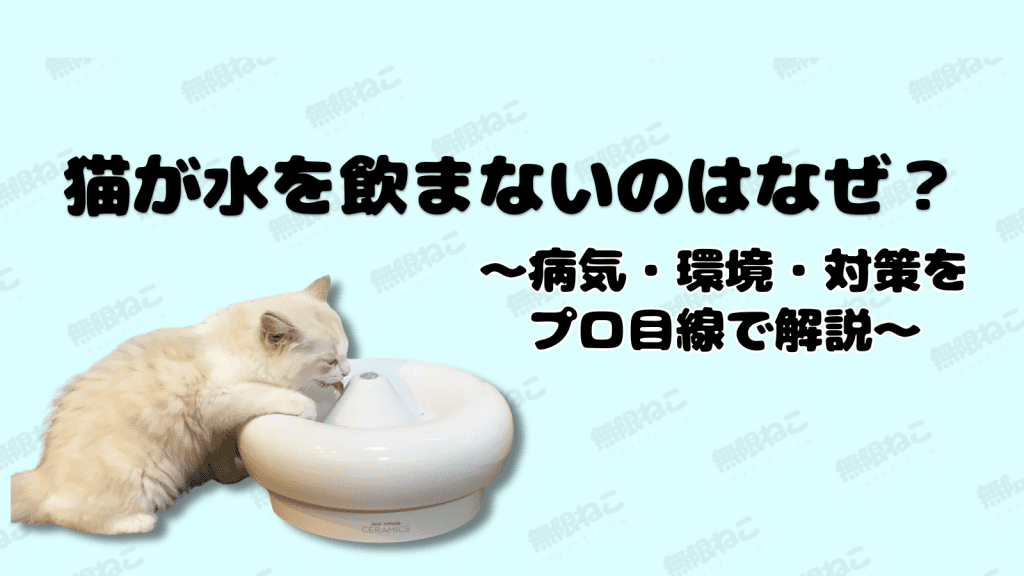
猫が水を飲まない理由とは?
なぜ猫は水を飲まなくなってしまうのでしょうか?
まず前提として、
猫の祖先は砂漠地帯に生息していたとされ、少ない水でも生き延びられる体の構造をしています。
そのため、現代の猫も「犬ほど水を飲まない」傾向があります。
特にウェットフード(缶詰など)を主食にしている猫の場合、食事からある程度の水分が摂取できるため、「あまり水を飲まなくても問題ない」と感じる飼い主さんも多いかもしれません。
しかし――。
水分不足が引き起こすリスク
猫にとって水分不足は腎臓や膀胱への負担となりやすく、以下のような症状につながることがあります:
- 尿路結石
- 膀胱炎
- 腎不全
これらは高齢の猫だけでなく、若い猫でも起こりうるため、「水を飲まない」は放置していいサインではありません。
実際にうちの猫を獣医師に相談したとき
我が家の猫も水をあまり飲まない時期があり、獣医師に相談したことがあります。
我が家は実は、少し珍しいケースなのですが、
- ドライフード・ウェットフード中心の食生活
→お水大好き!毎日ガブガブ飲む!
という時期から、
- 生肉・生魚中心の食生活
→水を一切飲まなくなる…
ということがありました。
確かに生のお肉には水分が多く含まれていますが、一切飲まない時期があまりにも長く続いたため、かかりつけの獣医師に相談したところ、
肉の水分で足りてるんでしょう。
本人(本猫)が必要なら飲みますよ。
というお話でした。
それから長らく水を飲まない猫として生活してきましたが、本猫は元気いっぱいに暮らしています。
今でもドライフードやウェットフードをあげた日にはたくさんのお水を飲んでおり、
たまたま我が家は自分で必要な水分量を調整できるタイプの性格だったようですが、身体は欲しているのに飲まずに過ごしてしまう猫がいるのも事実…
だからこそ、水分摂取に不安がある場合は、早めのチェックが大切だと感じています。
よくある解決パターン
獣医師に相談すると良く言われるアドバイスとしては、
「水を飲まない猫は“器の素材”や“設置場所”を変えてみると、急に飲み始めることがある」という話もあります。
ステンレスの器から陶器に変えたり、いつもの食事場所から離れた位置にも水を置いたところ、水を飲む頻度に少し変化が見られるようです。
猫にもっと水を飲ませるための5つの工夫
器の素材を変える
ステンレス・プラスチックを嫌がる猫もいます。
ガラスや陶器など、違う素材の器を試してみましょう。
複数箇所に水を置く
水飲み場が1ヶ所だけだと、猫が気づかないことも。
2〜3ヶ所に分けて置くと「見つけたら飲む」行動が増えやすくなります。
自動給水器・水流タイプを使う
流れる水を好む猫には、水がちょろちょろ流れるタイプの給水器がおすすめ。
動きがあることで興味を引き、飲む習慣がつくことも。
ウェットフードを併用する
普段ドライフード中心の猫には、1日1回でもウェットを取り入れることで水分摂取量を補いやすくなります。
氷やぬるま湯を試す(季節対応)
夏は氷を浮かべて興味を引く、冬はぬるま湯にして飲みやすくするなど、季節に合わせた工夫も効果的です。

水道から出てくる水を
そのまま飲むのが最高!
まとめ
猫が水を飲まないのは“よくあること”ではありますが、体調を守るためにも、水分補給の習慣はとても大切です。
ちょっとした器の工夫や環境の見直しで、水を飲み始める猫も多いので、「どうせ飲まないし…」とあきらめず、今日からできる対策を少しずつ試してみてください。
それでも飲む量が極端に少ない・体調に変化が見られるときは、早めの獣医師相談が安心です。
🐾 記事に登場したアイデアのチェックリスト
- □ 器の素材を変える
- □ 水飲み場を複数設置する
- □ 自動給水器の導入
- □ ウェットフードの活用
- □ 氷・ぬるま湯などの季節対応


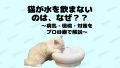
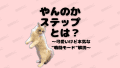

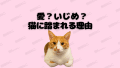

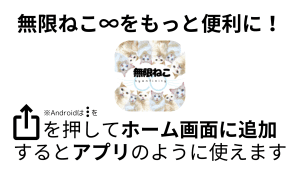
コメント